ケヤキニレ科 | 広葉樹
▲ ケヤキの板目

▲ ケヤキの木
▲ ケヤキの葉
原産地
国内では北海道を除き、全国的に分布しています。
ケヤキの良材は東北、関東、山陰などの他、九州の宮崎県などでも産出されています。
ケヤキの良材は東北、関東、山陰などの他、九州の宮崎県などでも産出されています。
比重
気乾比重:0.69(0.47~0.84)
強度
非常に硬い
▲ ケヤキの柾目
▲ ケヤキの紅葉
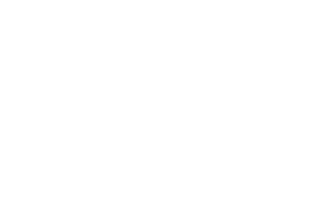
その他の名称
槻、ツキ
学名:[Zelkova serrata]
学名:[Zelkova serrata]
価格
高価
色調
辺材は灰白色で、心材は帯黄紅褐色。辺材、心材の色調が全く違う為、境界は明瞭ではっきりしていて見分けやすい。
特徴
ケヤキは強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているという木材として大変、優秀な特徴を持ち、外見的にも木目が力強く美しい事から古来より日本国内で最良の広葉樹として扱われてきました。
ケヤキは重硬で非常に硬い木材ですが加工はそれほど困難ではなく時間をかければ他の樹種と同じように問題なく行う事ができます。しかし、個体差が大きい樹種なので物によっては加工が困難な場合もあります。
大きな道管が年輪の周りに並んでいるので年輪がはっきりとしており、このハッキリとした年輪がケヤキの大きな特長のひとつとなっています。
肌目にはやや粗さがありますが手入れを美しい光沢がでます。
木材の業界ではケヤキを「青ケヤキ」と「赤ケヤキ」という名前で区別する事がありますが、この青ケヤキというには年輪幅の広い若い木を指します。青ケヤキは辺材の幅が広く辺材の方に反るという性質があるので赤ケヤキと比較するとかなり安価で取引されています。
関西では青ケヤキの事を「槻(つき)」と呼んでいるそうですが、この槻というのは暴れやすいケヤキの総称となっているようです。
また、如輪杢という特別な杢が出る事もあり、これは杢の中でも最高級の杢とされています。ケヤキには如輪杢の他にも玉杢、葡萄杢、牡丹杢、、泡杢、笹杢などといった特殊な杢が出る事がある為、それらの杢がでている木の場合、見た目に大きな差がでる樹種だと言えます。
国内でも有数とされる程、非常に魅力的な樹種である事から、ケヤキの魅力を世界に広めるという計画が立案された事があり、一時的にヨーロッパ方面へ輸出した事がありましたがヨーロッパの人達はケヤキの色があまり好みではなかったらしく思ったような成果は上げられなかったそうです。
ケヤキは重硬で非常に硬い木材ですが加工はそれほど困難ではなく時間をかければ他の樹種と同じように問題なく行う事ができます。しかし、個体差が大きい樹種なので物によっては加工が困難な場合もあります。
大きな道管が年輪の周りに並んでいるので年輪がはっきりとしており、このハッキリとした年輪がケヤキの大きな特長のひとつとなっています。
肌目にはやや粗さがありますが手入れを美しい光沢がでます。
木材の業界ではケヤキを「青ケヤキ」と「赤ケヤキ」という名前で区別する事がありますが、この青ケヤキというには年輪幅の広い若い木を指します。青ケヤキは辺材の幅が広く辺材の方に反るという性質があるので赤ケヤキと比較するとかなり安価で取引されています。
関西では青ケヤキの事を「槻(つき)」と呼んでいるそうですが、この槻というのは暴れやすいケヤキの総称となっているようです。
また、如輪杢という特別な杢が出る事もあり、これは杢の中でも最高級の杢とされています。ケヤキには如輪杢の他にも玉杢、葡萄杢、牡丹杢、、泡杢、笹杢などといった特殊な杢が出る事がある為、それらの杢がでている木の場合、見た目に大きな差がでる樹種だと言えます。
国内でも有数とされる程、非常に魅力的な樹種である事から、ケヤキの魅力を世界に広めるという計画が立案された事があり、一時的にヨーロッパ方面へ輸出した事がありましたがヨーロッパの人達はケヤキの色があまり好みではなかったらしく思ったような成果は上げられなかったそうです。
用途
主に建築材、家具材など。特にお寺の建築にはケヤキが欠かせないものとなっています。
家具の中でも和家具の材料としてケヤキは特に有名で、和箪笥、和机、ちゃぶ台などが作られていますが、近年では住宅が洋風化しケヤキの豪快な木目は住宅の雰囲気にあまり合わない事から家具の材料としての需要は昔ほどなくなってきているようです。
ケヤキのその他の用途としては和太鼓の胴の部分やお盆、お椀などの漆器があげられ、これらの加工品の材料としては現在でも非常に価値が高いとされています。
世界遺産に指定されている奈良県の正倉院の最も由緒のある宝物として知られている「赤漆文欟木御厨子(せきしつぶんかんぼくのおんずし)」はケヤキで作られており、この1300年経っているとされる宝物を見てもケヤキが如何に優れた木材であるかが分かります。
家具の中でも和家具の材料としてケヤキは特に有名で、和箪笥、和机、ちゃぶ台などが作られていますが、近年では住宅が洋風化しケヤキの豪快な木目は住宅の雰囲気にあまり合わない事から家具の材料としての需要は昔ほどなくなってきているようです。
ケヤキのその他の用途としては和太鼓の胴の部分やお盆、お椀などの漆器があげられ、これらの加工品の材料としては現在でも非常に価値が高いとされています。
世界遺産に指定されている奈良県の正倉院の最も由緒のある宝物として知られている「赤漆文欟木御厨子(せきしつぶんかんぼくのおんずし)」はケヤキで作られており、この1300年経っているとされる宝物を見てもケヤキが如何に優れた木材であるかが分かります。
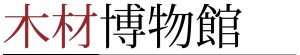














 トップページ
トップページ